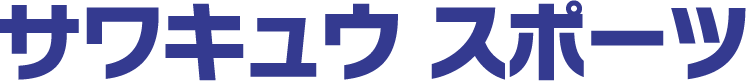卓球のダブルスは、シングルスとは全く異なる魅力と奥深さを持つ競技です。特に「サーブ」は、その独特なルールと戦術が勝敗に直結する重要な要素。「シングルスでは強いのに、ダブルスだとなぜか勝てない…」その原因は、サーブの考え方にあるかもしれません。
この記事では、卓球ダブルスのサーブに焦点を当て、初心者にも分かりやすく基本ルールから、試合で勝つための戦術、パートナーとの連携テクニックまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたのダブルスの試合運びが劇的に変わるはずです。
1. まずは覚えよう!卓球ダブルスサーブの基本ルール
ダブルスのサーブには、シングルスにはない独自のルールが存在します。これらを正確に理解することが、試合をスムーズに進めるための第一歩です。
1-1. サーブは必ず対角線に
ダブルスの最も特徴的なルールは、サーブのコースが限定されることです。サーバーは、自分のコートの右半面(フォアサイド)から、相手コートの右半面(相手のフォアサイド)へ、対角線上にサーブを出さなければなりません。。ボールが自陣または相手陣の左半面にバウンドした場合、失点となります。このルールにより、レシーバーはコースを予測しやすくなりますが、サーバーは回転や長短で工夫を凝らす必要があります。
1-2. 複雑なサーバーと打球の順番
ダブルスのサーブとラリーの順番は、公平性を保つために厳密に決められています。混乱しないように「レシーブした選手が次にサーブする」と覚えると良いでしょう。
- サーブの交代:サーブは2本ずつ交代します。A選手が2本サーブを出したら、次は相手ペアの選手(前のラリーでレシーブした選手)にサーブ権が移ります。
- 打球の順番:ラリー中は、ペアの2人が交互にボールを打ちます。例えば、A選手(サーバー)→X選手(レシーバー)→B選手(Aのパートナー)→Y選手(Xのパートナー)→A選手…という順番で打球が続きます。同じ選手が2回連続で打つと失点となります。
- ゲームごとの交代:ゲームが変わると、サーブ権が相手ペアに移ります。例えば、第1ゲームでA・Bペアが最初にサーブした場合、第2ゲームではX・Yペアが最初にサーブします。この時、X・Yペアのどちらがサーブを始めても構いません。
1-3. シングルスと共通の基本ルール
ダブルス特有のルールに加え、サーブに関する基本的なルールはシングルスと共通です。これらも遵守しなければなりません。
- 手のひらを開いてボールを静止させる。
- トスは垂直方向に16cm以上上げる。
- ボールが頂点から落ちてくるところを打つ。
- 打球の瞬間は、フリーハンドや体で相手からボールを隠してはならない。
これらのルールは国際卓球連盟(ITTF)や日本卓球協会(JTTA)によって定められており、違反すると失点となります。
1-4. レットと順番間違いの対処法
試合中には意図しない事態も起こります。
- レット(やり直し):サーブがネットに触れてから正しい相手コートに入った場合は「レット」となり、サーブのやり直しになります。
- 順番の間違い:もしサーバーやレシーバーの順番を間違えた場合、審判は誤りが発見され次第プレーを中断します。ラリー中に気づいた場合はそのラリーをレットとし、ラリー終了後に気づいた場合はその得点を有効とした上で、次のプレーから正しい順番に戻して試合を再開します。
2. 勝敗を分ける!ダブルスサーブの戦術と考え方
ダブルスで勝つためには、ルールを覚えるだけでは不十分です。サーブを「いかに戦術的に使うか」という視点が不可欠になります。
ダブルスのサーブは、サービスエースを狙うものではなく、パートナーの3球目攻撃をアシストするための「布石」である。
2-1. 「作る」サーブを意識する:3球目攻撃への布石
ダブルスにおけるサーブの最大の目的は、パートナーが次に打つ「3球目」で攻撃しやすいボールを相手に返させることです。これを「作る」サーブと呼びます。自分がサーブを出した次のボールはパートナーが打つため、自分の得意なサーブよりも、パートナーが攻撃しやすい返球を誘導できるサーブを選択することが絶対的な原則です。
2-2. 基本は「短く、低く」:下回転とナックルサーブの重要性
パートナーが3球目攻撃をしやすくするためには、相手のレシーブの種類を限定させることが重要です。そのため、ダブルスでは短い下回転サーブや、回転のないナックル(無回転)サーブが主体となります。これらのサーブは、相手に強打されにくく、「ツッツキ」のような予測しやすい返球を誘いやすいためです。逆に、複雑な横回転サーブは相手のレシーブの選択肢を増やし、パートナーが対応しづらくなるリスクがあります。
2-3. コース取りの極意:なぜセンターラインを狙うのか?
サーブのコースは対角線と決まっていますが、その中でも狙うべきはセンターライン付近です。右利きの選手にとって、体の中心に近いコースは窮屈で打ちにくく、フォアとバックのどちらで処理するか迷いやすいためです。ここにシンプルで予測しやすいサーブを出すことで、返球コースをさらに限定させ、パートナーが狙い球を絞って3球目攻撃を仕掛ける絶好の状況を作り出せます。
2-4. レシーブ有利の時代とチキータ対策
近年、「チキータ」と呼ばれる攻撃的なバックハンドレシーブ技術の発展により、ダブルスではレシーブ側が有利とさえ言われています。サーブコースが限定されているため、レシーバーは待ち構えて強力なチキータを打ち込めるからです。これに対抗するためにも、サーブの質がより一層重要になります。低く、回転が分かりにくいサーブを出すことで、相手に安易なチキータをさせず、甘い返球を誘うことが現代ダブルスの鍵となります。
3. ペアの連携を高める実践テクニック
ダブルスは「1+1=2」ではなく、連携次第で「3」にも「4」にもなる競技です。サーブを起点としたペアの連携は、その最たる例と言えるでしょう。
3-1. サーブ後の動き方(ポジショニング)
サーブを打った選手は、その場に留まっていてはいけません。パートナーが打球スペースを確保できるよう、素早く移動する必要があります。特に右利き同士のペアの場合、サーバーは打球後、時計回りに円を描くように後方へ下がり、パートナーが前に入るスペースを作ります。この動きが滞ると、お互いの邪魔になったり、空いたスペースを相手に突かれたりする原因になります。
3-2. 勝利の鍵を握る「サインプレー」
「どんなサーブを出すか」「どこを狙うか」といった戦術を、パートナーと瞬時に共有するために不可欠なのがサインプレーです。通常、サーバーはサーブを出す直前に、台の下など相手に見えない位置でフリーハンドの指を使ってサインを出します。
- 指1本:下回転サーブ
- 指2本:横回転サーブ
- グー:ナックル(無回転)サーブ
このように事前にサインを決めておくことで、パートナーはサーブの種類を把握し、返ってくるであろうボールを予測して3球目攻撃の準備に入ることができます。サインはペアの生命線であり、緊密なコミュニケーションの証です。
3-3. ペアの組み合わせを考慮したサーブ戦略
ペアの利き腕の組み合わせによっても、サーブ戦略は変わってきます。
- 右利きと左利きのペア:最も有利とされる組み合わせです。打球後の動線が交錯しにくく、スムーズにポジションチェンジができます。また、左利きの選手はフォアハンドでレシーブしやすいため、より攻撃的な展開を作りやすいです。
- 右利き同士のペア:動きが重なりやすいため、サーブ後の移動をより意識する必要があります。サーブは、パートナーが回り込んでフォアハンドで攻撃しやすいように、相手のバックサイド深めを狙うなどの工夫が求められます。
4. さらなるレベルアップを目指して:サワキュウスポーツで本格指導
ここまでダブルスのサーブに関するルールと戦術を解説してきましたが、理論を実践で活かすには質の高い練習が不可欠です。特に、パートナーとの連携や複雑な状況判断は、独学だけでは習得が難しい部分もあります。
「もっとダブルスで勝ちたい」「専門的な指導を受けたい」とお考えなら、ぜひサワキュウスポーツにご相談ください。
サワキュウスポーツでは、初心者から上級者までレベルに合わせた卓球スクールを開講しており、経験豊富なコーチがダブルス特有のサーブ戦術、レシーブ、ポジショニングなどを丁寧に指導します。また、店内では最新のラケットやラバーなどの卓球用品も豊富に取り揃えております。あなたのプレースタイルに合った用具選びも、勝利への近道です。
5. まとめ
卓球ダブルスのサーブは、単に試合を始めるための一打ではありません。それは、パートナーと連携し、得点を「作り出す」ための、戦術的な第一歩です。
本記事で解説したポイントをまとめます。
- ルールを遵守する:対角線のコース、2本交代、交互打球の順番を正確に守る。
- 戦術的に考える:エースを狙うのではなく、パートナーの3球目攻撃のために「作る」サーブを意識する。
- 基本を徹底する:サーブは「短く、低く」。下回転とナックルを主体に、センターライン付近を狙う。
- 連携を磨く:サーブ後の素早い移動と、サインプレーによる意思疎通を徹底する。
これらの知識を武器に、パートナーとコミュニケーションを取りながら練習を重ねることで、あなたのダブルスは必ず進化します。ぜひ、次の試合から実践してみてください。